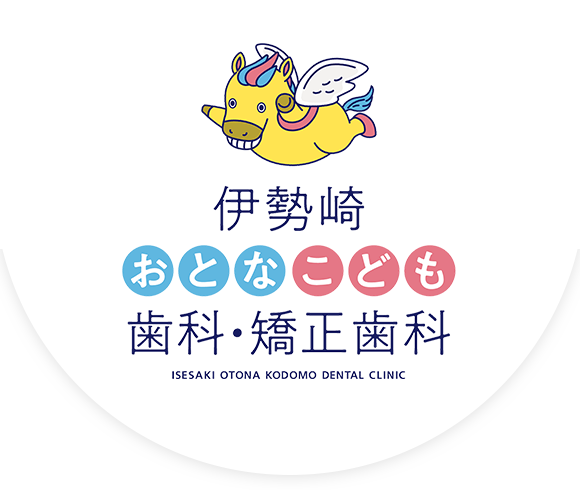離乳食教室|伊勢崎市の歯科医院
2024年12月24日
こんにちは、歯科医師の今野です。
この度、太田市にある尾島デンタルクリニックにて、離乳食教室が開催されました。
歯科医院で離乳食教室?
とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
歯科医院は「歯」を治すところ、歯が生えてから通うところ、というイメージが根強いからです。
ですが、近年、「食べる、話す、呼吸する」といった子供たちの「口腔機能」に心配事のある「口腔機能発達不全症」が問題視されています。
たとえば「お口ぽかん」「食べるのが遅い(いつまでもくちゃくちゃ噛んで飲み込めない)」「食べるのが早い(よく嚙まずに丸飲みしてしまっている)」「口呼吸」「滑舌が悪い」などなど…
こういった問題は実は歯が生える前の乳幼児期から始まっている、ということが近年の研究により分かってきました。
まずは離乳食開始時、離乳食を開始するタイミングは合っているでしょうか?
離乳食を開始できるのは首が据わってから。
首が据わるのは生後3~4か月頃のため、5~6か月頃から離乳食開始していれば問題ありません。
その時期になっても首が据わっていなければ小児科へ相談しましょう。
逆にそれ以前、生後3~4か月のまだ首が据わっていない時期に離乳食開始していないでしょうか。
多くの保護者の方は子どもの成長を楽しみにしています。
できるだけ早く成長した姿を見たいのが親心です。
ですが、その子の本来の機能発達に合っていない早期の離乳食開始は、機能発達不全を起こしてしまうこともあり、注意が必要です。
また、離乳食開始後も離乳食をとるときの姿勢やスプーンの種類の選択も大切です。
離乳食のステップアップは、口の機能をしっかり育てるためにも成長に即した栄養をしっかりとるためにも重要ですが、育児書通りに「〇ヶ月になったから次にステップアップしよう」と月齢通りに進めると、実際の口腔内の成長(歯の萌出状況や口唇、舌の動きなど)が追いついていないこともあります。
離乳食も奥が深いですね。
伊勢崎おとなこども歯科・矯正歯科では設備の関係上、離乳食教室は行っておりませんが、太田院の尾島デンタルクリニックにて、管理栄養士による離乳食教室を今後も予定しております。
もしご興味がありましたら、是非お問い合わせください。
噛ミング30で健康に!
2024年11月25日
こんにちは、歯科医師の青山です。
食欲の秋がやってきました。
たくさん美味しいものであふれる季節ですが皆さんは食べる時、ひと口何回噛んでいるか数えたことがありますか?
よく噛んで食べるこで身体にいいことがたくさんあります。
厚生労働省では「噛ミング30(カミングサンマル)」というキャッチフレーズのもと、ひと口30回以上噛むことを目標としています。
よく噛むことで
①満腹中枢が刺激され食べ過ぎ防止、交換神経が刺激され代謝が活発になり消費カロリーが増加することで肥満予防ができる。
②お口の周りの筋肉が鍛えられられ、小児では顎や発音などの発達を促す、高齢者では誤嚥のリスクを減らすことができる。
③脳の血流が良くなり脳の働きが活性化する。
などの良い効果が得られます。
お子さんからご高齢の方まで噛ミング30で健康をつくっていきましょう!
最近咬みにくいな、うちの子の咬み合わせは大丈夫なのかなど些細な心配ごとでも当院にご相談くださいね。
お口の“細菌”について、知ろう!|スマーク伊勢崎の歯科医院
2024年10月24日
こんにちは、歯科医師の小林です。
「虫歯」や「歯周病」という名前は聞いたことがあると思いますが、原因は何だかご存知ですか?
砂糖、唾液、歯磨き、噛み合わせ、生活習慣等、原因は1つではありませんが、虫歯も歯周病も『細菌』が関係しています。
今回は、お口の中の細菌についてお話をしていきます。
①虫歯菌
代表的な細菌は「ミュータンス菌」です。
食べ物や飲み物に含まれる糖分を分解し、それらを栄養として菌の周りにネバネバした「プラーク」を作ります。さらに、虫歯菌は酸を放出するため、歯の表面が溶けてしまい、虫歯になってしまうのです。
また、乳酸飲料等に多く含まれる「ラクトバチラス菌」も、腸内では良い働きをすると言われていますが、お口の中では虫歯をつくる原因菌となっています。
②歯周病菌
歯周病菌は種類が多く、プロフィロモナス・ジンジバリス、トレポネーマ・デンティコラ、スピロヘータ等、呪文のような名前の細菌がたくさん存在します。
酸素があっても大丈夫な菌もいれば、酸素が大嫌いで、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の境目の深い部分や、蓄積したプラークなど隠れたところで歯周病を進行させる菌もあります。
③カビ菌
体調不良が続き免疫力が低下したり、お口が乾燥しやすい方は「カンジダアルビカンス」とよばれるカビ菌が増殖しやすくなります。
口腔カンジダ症を発症すると、お口の粘膜が赤く腫れたり白くなったり、ピリピリとした痛みを伴うことがあります。
お口の中には何百種類もの細菌が存在し、一人当たり何億もの細菌がいると言われています。目に見えないからこそ、ご自分のお口に合わせた対策をし、身体を整えたいものですね。
当院では、「位相差顕微鏡」という特殊な顕微鏡を用いて、お口の中の細菌の種類を確認しています。気になる方はぜひお気軽にご相談ください!
矯正で綺麗に|スマーク伊勢崎の矯正歯科
2024年9月24日
皆さんこんにちは。歯科医師の菅原です。
最近矯正希望の患者さんが増えて、よく質問されることがあります。
それは「矯正で顔って変わりますか?」です。
皆さんの永遠の悩み「もっと綺麗に、もっとかっこよく」。
そんな気持ちが表れている言葉です。
結論から言うと変わらない場所と変わる場所があります。
矯正とは歯を理想的な位置に動かして噛ませてあげる治療法です。
矯正治療で綺麗になるのは
①笑った時の歯の見え方
②歯の裏打ちがある唇周り
です。
よく「顎の歪みって治りますか?」「骨格って変わりますか?」と聞かれることがあります。
噛み合わせと勘違いされている方がよくいますが、顎の歪みは顎の骨と顎の関節が関係しています。
さらには表情や顎を動かしている筋肉も関係します。
噛み合わせは、実はその最後にきます。
なので噛んだ時に顔が歪んでいるのは歯並びの影響も受けますが、笑った時やその他の表情や顎や骨格の歪みは矯正では改善されません。
皆さんよくよく考えてみてください。歯をくっ付けて笑う人は居ませんよね?
なので噛み合わせが変わったから、表情が変わるわけではありません。
矯正をして綺麗になる人は、歯並びが変わる事で自分に自信がついて笑顔が増える人です。
笑顔が増える人はシワや弛みが少なくなり、血行も促進されるのでアンチエイジングが期待されます。
これが本当に矯正での綺麗、カッコいい人だと思います。
逆に矯正に対して不安、痛くて辛い、大変などネガティブな感情をお持ちの方はドンドン老けて行き、綺麗・カッコいい顔からは遠くなってしまいます。
なので矯正への不安を取り除くことが大切だと思います。
当院ではカウンセリングや担当医からの説明で、出来るだけ患者さんの希望に応える事や、不安を取り除いて行くような治療を心がけています。
矯正を通して患者さんの「今よりも綺麗に、今よりもカッコ良く」をサポート出来るように頑張って行きます。
何か質問がある場合は当院のスタッフにお気軽にご相談ください。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について
熱中症と虫歯|スマーク伊勢崎の歯科医院
2024年8月21日
こんにちは、歯科医師の藤巻です。
蒸し暑い日が続いていますが、この季節熱中症対策としてスポーツドリンクや塩のタブレットキャンディなど持ち歩く方も多いのではないでしょうか。
今回は熱中症と虫歯についてお話をしていこうと思います。
この季節は特に熱中症対策のため、こまめな水分摂取を推奨されています。
実は歯科の観点からもお口の中を潤すのはよい口腔内環境を作ることにも大切です。
しかし、水分なら何でもよいというわけではありません。
もちろん部活や仕事、運動時など大量の汗をかいた際、スポーツドリンクや塩タブレットなどは、塩分や糖分を効率よく摂取するのには大変有効です。
ただ、こうしたものの中には歯を溶かす酸や虫歯の原因になる糖がたくさん含まれ、お口の中が酸性の状態になります。
したがってこまめな水分摂取をスポーツドリンクで行うと、お口の中は常に歯を溶かし、虫歯になりやすい環境になってしまうのです。
では虫歯対策をしながら水分補給をするにはどうしたらよいのでしょうか?
まずはお口の中を酸や糖に長時間さらさないことがポイントです!
スポーツドリンクなどを飲んだ後、水やお茶など糖分を含まない飲み物を飲むことでお口の中を酸性度を薄めることができます。
ただお茶は歯の着色につながるタンニン(ポリフェノールの一種)という成分が含まれるので、着色が気になる方はポリフェノールの含有量の少ないお茶を選んでみるのもよいと思います。
また、飲んだ後にうがいするだけでもお口の中の酸性の状態は正常に近いところまで戻すことができるのです。
このようにこまめな水分摂取に少し工夫を加えて、熱中症と虫歯どちらも上手に対策をしていきましょう。
緑茶は歯にいい?|スマーク伊勢崎の歯科医院
2024年7月22日
こんにちは、歯科医師の女屋です。
緑茶は体にいいと聞いたことはあるかもしれませんが、歯にもいいのでしょうか。
緑茶に含まれるカテキンには、むし歯や歯周病に対する予防効果があります。
カテキンはむし歯や歯周病の原因になる菌の増殖を抑え、それらの病気への予防効果があるだけではなく、嫌なにおいを発生させるような菌も抑制して口臭予防にもなります。
また、緑茶に含まれるフッ素の化合物は初期のむし歯を元通りに治す「再石灰化」を促す重要な役割を果たします。
高齢者を対象とした最近の研究において、緑茶を1日に4杯以上飲む人は飲んでいない人に比べて約1.6本歯が多かったとの結果があります。
これは、日常的な緑茶の摂取が歯の健康維持に関係している可能性を示しています。
以上のことから、緑茶の摂取は歯に対して良い影響を与えると考えられます。
しかし、就寝前に飲む場合には注意が必要です。
緑茶にタンニンという成分が含まれこれが歯にくっつくことで歯が着色してしまう原因になり、カフェインは良い睡眠を妨げる可能性があります。
就寝前に飲む場合は軽く水でうがいをする、飲むのは就寝の数時間前までにするなど注意する必要があります。
日頃からご自身での歯磨きや歯科医院での定期受診をしっかり行った上で、積極的な緑茶の摂取をしてみてはいかがでしょうか。
仕上げ磨きについて|伊勢崎の小児歯科
2024年6月20日
こんにちは、歯科医師の青山です。
今回は仕上げ磨きについてお話します。
お子さんが小さいうちは自分で上手に磨けないため、みなさん仕上げ磨きを行っているかと思います。
その仕上げ磨きは何歳まで行った方がいいかご存知ですか?
一般的には小学校高学年くらいまでと言われています。
意外と長くて驚く方が多いです。
乳歯からすべて永久歯に生え変わるのが12歳頃と言われているので、その時期まで必要とされています。
仕上げ磨きは
①乳歯や生えたばかりの永久歯は性質上むし歯になりやすい
②生え変わりの時期は背の低い歯があるなど歯磨きが難しい
③お口の中の変化に気付くため
以上のことから重要です。
とは言え、いずれ仕上げ磨きを卒業し、お子さん自身の歯磨きでむし歯を予防していく必要があります。
また、仕上げ磨きのポイントが分からない。
うちの子、今自分でどのくらいまで磨けているの?
どんな歯ブラシを使ったらいいの?
など不安があるかと思います。
年齢に応じた正しい歯磨きの仕方などサポートいたしますのでぜひご相談ください!
口腔機能支援士|スマーク伊勢崎の歯科医院
2024年5月22日
こんにちは、歯科医師の今野です。
先日、日本小児口腔発達学会における口腔機能支援士の資格を取得しました。
近年、お口の機能に困りごとのある子どもたちが増えています。
食べるのが遅い
あまり噛まずに丸のみしている
食べるときにクチャクチャ音を立てて注意しても治らない
赤ちゃん言葉が気になる
いつもお口がぽかんと開いている…などなど
このようなことはお口の機能の問題が関係している場合があります。
こういったお口の機能の問題を耳鼻咽喉科や小児科など多職種と連携を取りながら対応していくことも歯科医院の役割であり、口腔機能支援士の仕事です。
お口がぽかんと開いていることによって、舌の位置が下がると、上顎が上手く成長せず、歯の並ぶアーチが小さくなり、歯並びが悪くなります。
すると、気道が狭くなって鼻呼吸が難しくなります。
いびきをかく子もいます。
すると睡眠の質が下がって、身体面ではホルモンバランスの乱れ、精神面では集中力の低下や学力の低下、気持ちや心の不安定さ、それによるコミュニケーション能力の低下も生じます。
睡眠障害を持っている子どもたちの約40%がADD、ADHD、および学習障害を示しているそうです。
また、それによりADHDと誤診される子どもたちも増えています。
「呼吸の問題を歯科に相談する」とはあまり馴染みがないかもしれません。
鼻閉やアデノイド肥大、中咽頭・口蓋扁桃肥大…こういった器質的問題は耳鼻科の先生が専門です。
一方で、歯列矯正、口腔筋機能療法、は歯科の分野です。
何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
正しい「歯磨き」とは?|スマーク伊勢崎の歯科医院
2024年4月24日
こんにちは、歯科医師の小林です。
「ちゃんと歯磨きしているのに、虫歯になった」
「歯磨き中に出血します。歯周病かもしれない」
そんなお悩みは、ありませんか?
さて、質問です。
使用しているのは、歯ブラシだけ、ですか?
実は、歯ブラシだけでは約60%しか磨けていない、と言われています。
驚きですよね!
しっかり歯を磨いたつもりでも、歯ブラシの毛先が届きにくい歯と歯の間は残念ながら完全に磨くことができません。
そのため、歯間ブラシやフロスを使うことも大切です。歯ブラシと併用することで、100%近くまで磨けるといわれています。
歯間ブラシにはサイズがあり、太さが異なります。
適切な歯間ブラシを使用しないと、歯を磨いているはずが歯茎を傷つけてしまったり、隙間に通しているだけで磨けていないかもしれません。
また、フロスもただ通してればよいわけではありません。歯の形に添わせて動かしながら磨き、隣り合った歯も同様に磨くことで、歯垢を落とすことができます。
はじめのうちはフロスを通すと痛い、難しい、とおっしゃる方もいらっしゃいます。
最初から完璧に使える方は少ないですが、鏡を見ながら続けてくださるうちに、徐々に上手に使えるようになる方もたくさんいらっしゃいます。
まずは、歯ブラシでの磨き方を確認することも大切です。
毛先の当て方によって汚れの除去効率が変わります。
当院では、歯ブラシの使用方法はもちろん、患者さん一人一人のお口の状態に合わせたおすすめの補助器具や歯磨き粉をご紹介しています。
歯ブラシの当て方なんて、聞いたことがない。
歯間ブラシを使っているけれど、私のお口にはこれであっているのかしら?
フロスの正しい通し方を知りたい!
少しでも疑問に思うことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!
子供の矯正|伊勢崎市の小児歯科
2024年3月18日
こんにちは、歯科医師の菅原です。
今回は臨床しているとよく出会う子供の矯正の疑問について説明します。
①「いつからやれば良いのですか?」
これは良くある質問です。
こどもの矯正は出来る時期が決まっています。
年齢は5〜8歳ぐらいが適齢期の事が多いですが、歯並びによって変わって来ます。
前歯が大人の歯に生え変わったら行うのが一般的です。
伊勢崎おとなこども歯科では子供の矯正には2つの種類があり小児矯正と予防矯正と言うものが存在します。
どちらを行うかはそれぞれの特徴を矯正の無料相談の時に説明させて頂き、提案させてもらっています。
②「子供の時は歯並び綺麗だったのに大人の歯になったらガタガタしてた。これは時間が立つと治りますか?」
この質問も多く頂きます。
お答えとしてはあまり改善しないです。
上顎の成長は早く、10歳前ぐらいからはあまり成長しなくなってきます。
ピークは6歳より前になるので、ガタガタが取れるほどに成長させるには専門的な器具が必要になってきます。
下顎は上顎よりも遅れて大きくなるので、ピークは10〜15歳くらいです。
ですが、下顎は実は上顎より大きくはならないので上顎が小さいとガタガタは良くなりません。
なので大人の歯に生え変わってできたガタガタは、専門的な装置じゃないと改善できないという事です。
最後に受け口についても大切なので説明します。
受け口は子供の時に矯正しておいたほうが良い歯並びの代表です。
受け口だけは放置して成長期が終わると上顎より下顎の方が大きくなってしまうので、おとなの矯正の時は手術が必要になるケースがほとんどです。
当院では受け口の人には早期の矯正をオススメしています。
今回は子供の矯正で良くある質問を取り上げましたが、参考になりましたか?
当院では矯正の無料相談を行っています。
ご予約の場合は当院のサイトまたはお電話にて承っております。
何か不明な点が有れば当院のスタッフまでお気軽にご相談ください。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について