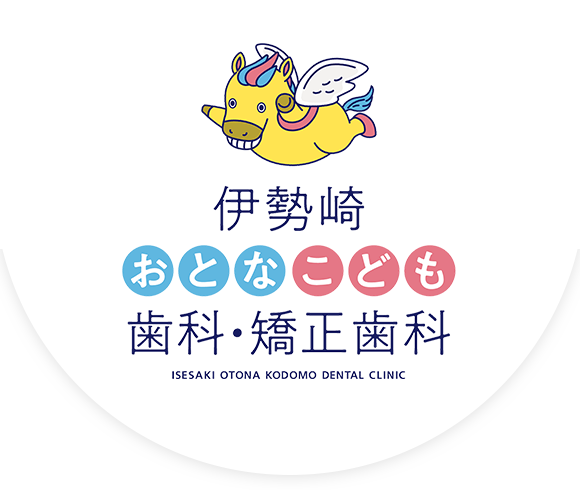歯石について|伊勢崎市の歯科医院
2023年5月19日
こんにちは、歯科医師の女屋です。
今回は歯石についてお話しいたします。
歯石はとったほうがいいと聞くことがよくあると思いますが、それはなぜでしょうか?
歯石はプラーク(細菌の塊)がかたまったものです。
実は歯石そのものに害はありませんが、歯石はザラザラしているので表面にプラーク(細菌の塊)がつきやすくなるため、除去する必要があるのです。
歯石ができる速さには個人差があり、唾液などの成分やpHが影響すると考えられています。
2週間ほどでほぼ成熟する人もいれば、数ヶ月から数年かかって形成される場合もあります。
また、面白いことに経管栄養により食物を摂取している人は、そうでない人よりも口の中に食物が入らないにもかかわらず歯石形成が多いことが報告されています。
このことは、食物など口の中に入る物質の成分が歯石形成を促進したり抑制したりする可能性を示しています。
歯石は歯ブラシなどご自身ではとれないため、歯医者で専用の機械でとってもらう必要があります。
歯石をとってほしい方はぜひ一度ご相談ください。
子どもの歯と大人の歯の交換について|伊勢崎市の歯科医院
2023年4月24日
こんにちは、歯科医師の酒井です。
今回は普段後相談をいただくことの多い、
生え変わりの時期の大人の前歯の生え方についてのお話をしていこうと思います。
前歯の交換は、6歳ごろに下の前歯から始まり、それから1年後くらいに上の前歯が続きます。
もちろん個人差はありますし、もともと足りないこともありますから、
もし生えてくる時期が遅く心配な場合はレントゲン撮影を行って確認することもできますので、
気軽にご相談ください。
さて、本題に戻りますが、相談をいただくことが多い内容として
「子どもの歯と大人の歯が同時に生えてきてしまった」というものがあります。
特に下の前歯でこのような相談をいただくことが多いです。
確かに同じところに同時に2本の歯が生えていたら、見た目のインパクトもありますし、
将来的に歯並びが悪くなったりしないのか不安になりますよね。
ただ、結論から申し上げると、一時的に2本同時に生えていたとしても
問題が無いことが多いです。
実は歯の生え変わりは必ずしも真下から大人の歯が生えてくるとは限りません。
上の前歯はエレベーター式の交換と言い、真下から生えてくることが多いですが、
下の前歯はエスカレーター式の交換と言い、子供の歯の後ろから大人の歯が生えてくることがほとんどです。
とは言っても大切なお子様の歯並びのことで不安にもなるでしょうし、
子供の歯を抜いてあげないと大人の歯が生えてきにくい状態になっていることもあるので、
不安であれば気軽に相談いただければと思います。
嫌がる赤ちゃんの歯を磨くには?
2023年3月17日
こんにちは、歯科医師の澤野です。
皆さんは赤ちゃんの歯磨き、スムーズにできていますか?
お父さんお母さんの「しっかり虫歯予防をしてあげたい!」という気持ちとは裏腹に、なかなか歯磨きをさせてくれない赤ちゃんが多いと思います。
今回はなぜ歯磨きを赤ちゃんが嫌がるのか、そしてどうしたらスムーズにお口のケアをする事が出来るのかを一緒に考えていきたいと思います。
そもそもなぜ赤ちゃんは歯磨きを嫌がるのでしょうか。
理由は以外と単純で、皆さんの仕上げ磨きが痛いから赤ちゃんが嫌がっているという事が多いです。
皆さんは歯ブラシ、正しく持てていますか?歯ブラシの正しい持ち方はエンピツと同じ持ち方です。
力加減は100~150グラム程度が正しいとされています。
持ち方が正しくないと必要以上に力が入ってしまい、赤ちゃんが痛みを感じる原因となってしまいます。
また、大人の歯磨きと同じように歯周ポケットまで磨けるよう、歯茎に歯ブラシの毛先を入れるように磨いていませんか?
赤ちゃんの歯にはまだ歯周ポケットケアは必用ありません。
歯面に対して直角に毛先を当てれば十分磨けています。また、上唇小帯(上の前歯の歯ぐき上部にあるひだ)に歯ブラシが当たっていませんか?
ここに歯ブラシが当たるととっても痛いので、上の前歯を磨くときはこの部分を指で覆ってあげるようにしましょう。
歯磨きの時の雰囲気もとても大切です。
なかなか磨かせてくれないとイライラしてしまうと思いますが、まずは歯磨きタイムを親子の時間として楽しむところから始めてみましょう。
YouTubeで歯磨きの歌の動画を流してみたり、頬を触るなどのスキンシップから歯磨きを始めるのは非常に効果的です。当院では子供の時からの口腔ケアが非常に大切だと考えております。
磨き方のアドバイスも行っておりますので、気軽にご相談いただければと思います。
歯に物が挟まるって、どんなサイン?|伊勢崎市の歯医者
2023年2月6日
こんにちは、歯科医師の小林です。
お食事の際、歯と歯の間に食べ物が挟まるとどうしても気になってしまいますよね。
「以前より歯と歯の間に食べ物が挟まりやすくなった」
「繊維質の物が詰まってしまい、煩わしい」
「もしかして、虫歯?」
そんな悩みを抱えている患者さんも少なくありません。
今回は、なぜ歯に物が挟まるのか、その原因についてお話ししていきます。
①歯と歯の間に虫歯がある
歯と歯の間は歯ブラシだけだとどうしても磨き残しが起きてしまい、気がつかないうちに虫歯になってしまいます。
歯の表面が溶けてザラザラしたり、穴が空いてくると、食べ物が挟まりやすくなります。
②歯茎の位置が下がった
歯周病により歯茎の位置が下がると、歯と歯茎の隙間が広がってきます。
また、歯茎の位置が下がる原因は歯周病だけではありません。
実は、サイズの合わない歯間ブラシを使用したり、誤ったフロスの通し方でも歯茎の位置が下がる原因となります。
③噛み合わせや歯並びに原因がある
歯と歯の間に隙間があいていたり、重なっている部分があると、食べ物が押し込まれやすく挟まる原因になります。
また、噛み合わせや歯ぎしりにより少しずつ歯が動いたりすり減ったりすることでも、食べ物が挟まりやすくなります。
このように、「歯と歯の間に挟まる」といっても原因は1つではありません。
お口に合わせた原因を判断して、治療を行うことが大切です。
また、正しい歯磨きの仕方を学ぶことも非常に重要です。
そのままにしておくと虫歯や歯周病が進行する原因にもなりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。
歯磨きは何のため?|伊勢崎市で予防歯科
2023年1月6日
こんにちは、歯科医師の女屋です。
本日はブラッシングの目的についてお話ししたいと思います。
ブラッシングでは歯についた細菌の塊であるプラークを除去すること、歯にフッ化物を供給することの2点が重要です。
今では歯磨き粉にフッ化物が入っているのは当たり前になっていますが、昔はそうでなく、ブラッシングといえば
プラークを除去する行為でしかありませんでした。
最近は歯磨き粉にいろいろな成分が入っていますが、確実に有効なのがフッ化物です。
ブラッシングで完璧にプラークを取り除くことは不可能で、普通はブラッシング後でも多少のプラークは残っています。
プラーク中の細菌が歯を溶かすのですがブラッシングと同時にフッ化物が供給されていると溶けた歯の組織を修復してくれます。
このように、フッ素イオンはブラッシングの不十分なところを守ってくれます。
寝る前にフッ化物が口の中に残っていると、寝ている間は唾液が出ないのでフッ化物濃度が相対的に高くなります。
唾液には自浄作用がありお口の中をきれいにしてくれますが、唾液の出ないときはかわりにフッ化物が歯を守ってくれるということです。
フッ素イオンが高濃度に含まれている歯磨き粉を使って歯を守っていきましょう。
妊娠中にお口の中に起こるトラブル
2022年12月24日
こんにちは、歯科医師の澤野です。
体調管理が難しい季節ですね。皆様どうぞご自愛くださいませ。
今回は妊娠中にお口の中に起こるトラブルについて一緒に考えていきましょう!
① 歯ぐきの腫れや出血
妊娠中は女性ホルモンの分泌が増えます。
それにより、お口の中の細菌が増える事があり、歯肉炎になりやすくなります。
その状態を放っておくと悪化してしまい、歯周病になる可能性があります。
歯周病になり歯周病菌が血液に入り込むと早産や低体重児出産のリスクが高まるので、注意が必要です。
② 口臭が強くなる
唾液の量が減少したり、女性ホルモンの分泌が変化したりする事で口臭が強くなる傾向にあります。
また、食生活が乱れたり、つわりによって十分な口腔ケアができない事も口臭の原因となります。
③ 虫歯ができやすくなる
つわりや食習慣の変化、唾液量の減少により、虫歯ができやすくなってしまいます。
妊娠中に気を付けて頂きたい事としては、歯周病や虫歯にならないように、口腔内の環境を整える事です。
つわりで口腔内のケアが辛い時は、小さなヘッドの歯ブラシで磨く、香料や味の強い歯磨き粉を避けるなどの工夫をしてみましょう。
また、どうしても磨くのが辛いときはぶくぶくうがいをしてできるだけお口の中の汚れを落とすようにしてみましょう。
ちなみに安定期(4~7か月)は歯科治療や検診に適している時期です。
後期に入ってお腹が大きくなったり、お子さんが生まれて忙しくなった後だとなかなか治療や検診を受けるのが難しくなると思いますので、何かお口の中に不安がある際は、この時期に相談しに来ていただくのがお勧めです。
妊娠中もお子さんが生まれてからも、お母さんのお口の中の環境はお子さんに大きく影響を及ぼします。
我々も全力でサポートいたしますので、普段よりお口の中の環境を整えていきましょう!
歯に色がつく|歯の着色
2022年12月5日
【どうして歯に色が付くの?】
皆さんこんにちは。歯科医師の澤野です。
今日は男女問わずお悩みの相談を受ける事が多い歯の着色についてお話します。
歯の着色の原因は大きく分けると外的要因と内的要因に分けられます。
外的要因としては、主に2つです。
① 飲食物やタバコによる黄ばみ(ステイン)
赤ワイン、コーヒー、紅茶、緑茶、チョコレート、カレーなどの色が強い飲食物やタバコを吸う事は、歯に着色を引き起こします。
歯の表面はぺリクルという唾液由来の膜で覆われているのですが、その膜に飲食物のタンニンやタバコのヤニが吸着する事で、歯が黄色くなってしまいます。
② 磨き残し
歯の汚れを十分に落とさず、歯垢が付いたままにして放置してしまうと、歯石となります。歯石は歯を黄色く見せるだけではなく、口臭の原因にもなります。
内的要因としても主に2つです。
① 生まれつき
歯の表面構造のエナメル質という部分が厚ければ厚いほど、歯は白くなります。
日本人は欧米人に比べてエナメル質が薄いので、欧米人に比べて歯が黄色く見えるのです。
② 加齢や薬の影響
加齢によって歯の黄ばみは目立っていきます。
また、薬の影響で歯が変色してしまう事があります。歯の形成期にテトラサイクリン系の抗生物質を大量にとると、副作用として歯の色が灰色がかったり、縞模様ができたりします。
さて、原因が分かったところで一緒に対策を考えていきましょう。
まずは当たり前ですが、色の付きやすい飲食物を避ける事は有効です。
また、正しくブラッシングを行うのも非常に大切です。歯の着色を落とそうとして、粒の大きい研磨剤が入った歯磨き粉を使用したり、力を入れてブラッシングするのは、エナメル質を傷つけてしまい、逆に歯の着色を進めてしまう可能性があります。
大切なのは、自分の歯の着色の原因を知った上で、正しく対処していく事です。ぜひ私達にお手伝いさせていただければと思いますので、歯の色に関してお悩みの際は、気軽にご相談いただければと思います。
👉 ホワイトニングについて
歯科治療の麻酔薬|伊勢崎市の歯科医院
2022年11月9日
こんにちは、歯科医師の酒井です。
今回は歯科治療に使われる麻酔薬に関してのお話をしたいと思います。
歯科治療は痛みを伴う処置を伴う処置が多く、患者様のストレスを軽減するために麻酔が必要になる機会が多いです。
麻酔は痛みを和らげるために必要なものではありますが、麻酔処置後に動悸がしたり、気分が悪くなるなど不快症状を認めることがあります。
最近、僕の患者様でも麻酔後にこのような体の異常が見られ、処置を中断した方がいらっしゃいました。
当院では初診時での問診にて、これまでの歯科治療で気分が悪くなったことがないか、麻酔をした後に不快な症状が出たことはないかなどはしっかりと確認してから治療を行います。
しかし今まで特に問題がなくても、久しぶりの麻酔であったり、当日寝不足であったり体調が万全でなかったりすると、予期しない症状が出ることはあるようです。
このような症状は、麻酔の痛みや麻酔に際しての不安などのストレスによるものであったり、麻酔薬に含まれるアドレナリンが原因となっていることがほとんどです。
どちらの場合でも基本的には時間をおくと回復する場合が多いです。
我慢していると状況が悪化する場合もありますので、もし体に不調を感じた場合にはすぐにお声がけください。
回復した後も治療をそのまま続けるか、大事をとって処置を見送るかは自由に決めていただいて大丈夫です。
僕自身も声をかけていただきやすい雰囲気づくりを心がけていきます。
口呼吸について
2022年10月26日
皆さんこんにちは、歯科医師の菅原です。
皆さん口呼吸って知っていますか?
「うちの子常に口を開けているんですよ」
「鼻が詰まって口でしか息が出来ないんです」
など親御さんから質問される事があります。
この様な兆候があるお子さんは口で息している可能性があります。
口で呼吸を行っているとどうなってしまうかと言うと、有名なのは風邪やウイルスなどにかかりやすくなります。
なぜかと言うと、お鼻の中は鼻毛やそれより細かい繊毛でウイルスや細菌をブロックし、また粘膜によりウイルスや細菌を絡め取り痰などで排出したり胃酸で無毒化します。
また鼻腔内を通ることで湿気を空気に与えることができ、湿気に弱い細菌やウイルスをブロックする事ができます。今流行りのコロナにも強くなります。
次に口呼吸に比べると鼻呼吸の方が体内に酸素を取り込む量を増やす事ができます。
体内の酸素の量を増やすことによって体の代謝をあげて痩せやすくなったり、睡眠の質がよくなり目覚めが良くなったり、ホルモンのバランスが整い成長などを促進したりと良いことが多いです。
ただ単にお鼻で呼吸しなさいと言うのは簡単ですが、そんなに簡単に出来る訳ではありません。
様々なステップがあります。このステップを教え、解決し、正しい鼻呼吸をできる様にするのが当院で行っている予防矯正の目的の1つです。
当院では予防矯正を通じてお子さんの成長や発育を手助けしています。
様々な装置はもちろん、アクティビティーと言われる運動を組み合わせることによって、しっかり鼻で呼吸ができる様にサポートしていきます。
何か質問があれば遠慮なくしてください。
舌小帯短縮症
2022年10月7日
こんにちは、歯科医師の今野です。
この頃、お子さんの話し方についてのご相談が増えてきました。
「舌っ足らずな話し方で」
「滑舌が悪くて」
「赤ちゃん言葉が抜けなくて」
などなど。
原因としては舌の筋力や動かし方といった機能的な問題もあります。
その場合は舌の筋力トレーニングや舌の使い方を学んでもらうというようなアクティビティを行いますが、器質的な原因もあります。
その原因のひとつが「舌小帯短縮症」です。
「舌小帯短縮症」とは、舌の裏側にあるスジのような組織が舌の先から歯茎の方に伸びているため、舌の動きが制限されてしまう先天性の異常です。
それにより赤ちゃんの時期に哺乳が難しかったり、3~5歳になっても発音がはっきりしなかったりします。
お家で確認する方法としては、舌を「あっかんべー」と前に突き出してもらった時に舌先がハート型になる状態です。
治療法は、「舌小帯切除術」といって、局所麻酔を使って、レーザーやメスで行います。
舌小帯が短いことにより、舌の動きが制限されると、滑舌が悪くなったり、食事しにくかったり、舌を上に持ち上げられないので歯並びや嚙み合わせが悪くなる原因にもなります。
それを治療するものです。
手術後は再癒着防止のために舌の体操を行う必要があります。
気になることがありましたらお気軽にご相談ください。