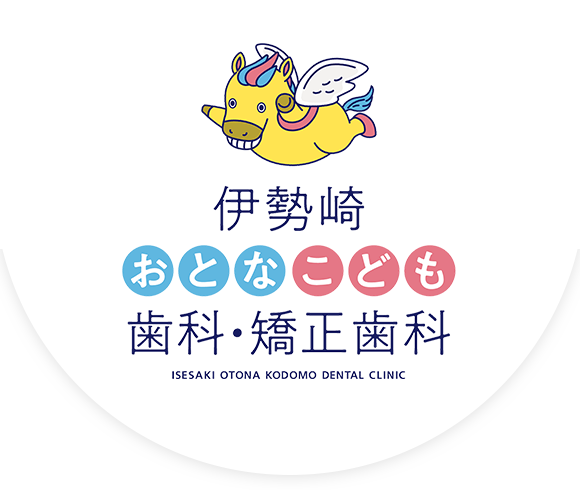歯磨きの後にうがいはしない方がいい?
2025年6月2日
こんにちは、歯科医師の女屋です。
みなさんは歯磨きの後お口をゆすぎますか?
歯磨き粉に含まれているフッ素(フッ化物)はむし歯予防に重要なので歯磨きの後はうがいをしすぎない方がいいと聞いたことがあるかもしれません。
実際、歯磨き後にうがいなしと比べてうがいしたほうが有意にフッ化物の濃度が低くなっていることを示した研究結果が報告されています。
しかし、歯磨き後は少しでもお口をゆすぎたいと思う方が多いのではないでしょうか。
多くの文献では、「10 mL以下の水による1回のうがい」であればむし歯を予防できる最低限のフッ化物の濃度を長時間維持できると結論づけております。
つまり、ティースプーン(小さじ)2杯分くらいの量の水ならばうがいして大丈夫ということですね。
また、歯磨き途中に歯磨き粉を吐き出すのを最小限にすること、歯磨き後2時間は飲食を控えるのもお口の中のフッ化物の濃度を保つのに有効です。
以上のことから年齢に応じた高濃度のフッ化物が配合歯磨き粉(成人であれば1,450ppm)を使用し、うがいしないか少量の水でうがいするのがむし歯予防に良いと言えそうですね。
もちろん歯磨きにはフッ化物以外にもいろいろな大切な要素があります。
当院では一人ひとりに合わせたブラッシング指導を行っており、ご要望に合った歯磨き粉のご提案もできます。
気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。
歯磨きはどのくらいすればいい?
2025年1月27日
こんにちは、歯科医師の女屋です。
毎食後歯磨きをしっかりされている方もいらっしゃれば、忙しくて夜1回しか磨けてないという方もいらっしゃると思います。
それでは、どのくらい歯を磨くのが望ましいでしょうか。
2016年の歯科疾患実態調査では毎日2回以上歯を磨く方は77%、毎日3回以上歯を磨く方は25%、毎日1回の方は約18%と報告されています。
このように、1日2回以上の歯磨きが一般化していると言えます。
お口の中にはバイオフィルムという細菌の塊が膜をはったものが存在しています。
これは例えば排水溝のぬめりのようなもので、放置すると病原性が強くなってむし歯や歯周病(歯を支える骨が溶ける病気)が進行してしまいます。
歯磨きの回数が増えれば、細菌の量が減りお口の中の環境が改善されます。
研究でも1日2回以上歯磨きを行うことで歯ぐきの状態を健康に保つことができ、それが歯の喪失を防ぐのに関係している可能性が高いことが示されています。
また、毎食後のブラッシングにより糖尿病や脂質異常症などの病気になるリスクが明らかに下がることを示した追跡研究もあります。
以上のことから、毎食後歯磨きを行うことでむし歯や歯ぐきの病気の予防だけでなく、糖尿病予防などの全身的な面でも有利になるといえます。
もちろん歯磨きは回数だけでなくどれだけ適切に行えているかも重要ですので、歯科医師、歯科衛生士の指導を受けることをおすすめします。
当院では予防歯科に力を入れていますので気になる方はぜひお気軽にご相談ください。
お口の“細菌”について、知ろう!|スマーク伊勢崎の歯科医院
2024年10月24日
こんにちは、歯科医師の小林です。
「虫歯」や「歯周病」という名前は聞いたことがあると思いますが、原因は何だかご存知ですか?
砂糖、唾液、歯磨き、噛み合わせ、生活習慣等、原因は1つではありませんが、虫歯も歯周病も『細菌』が関係しています。
今回は、お口の中の細菌についてお話をしていきます。
①虫歯菌
代表的な細菌は「ミュータンス菌」です。
食べ物や飲み物に含まれる糖分を分解し、それらを栄養として菌の周りにネバネバした「プラーク」を作ります。さらに、虫歯菌は酸を放出するため、歯の表面が溶けてしまい、虫歯になってしまうのです。
また、乳酸飲料等に多く含まれる「ラクトバチラス菌」も、腸内では良い働きをすると言われていますが、お口の中では虫歯をつくる原因菌となっています。
②歯周病菌
歯周病菌は種類が多く、プロフィロモナス・ジンジバリス、トレポネーマ・デンティコラ、スピロヘータ等、呪文のような名前の細菌がたくさん存在します。
酸素があっても大丈夫な菌もいれば、酸素が大嫌いで、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の境目の深い部分や、蓄積したプラークなど隠れたところで歯周病を進行させる菌もあります。
③カビ菌
体調不良が続き免疫力が低下したり、お口が乾燥しやすい方は「カンジダアルビカンス」とよばれるカビ菌が増殖しやすくなります。
口腔カンジダ症を発症すると、お口の粘膜が赤く腫れたり白くなったり、ピリピリとした痛みを伴うことがあります。
お口の中には何百種類もの細菌が存在し、一人当たり何億もの細菌がいると言われています。目に見えないからこそ、ご自分のお口に合わせた対策をし、身体を整えたいものですね。
当院では、「位相差顕微鏡」という特殊な顕微鏡を用いて、お口の中の細菌の種類を確認しています。気になる方はぜひお気軽にご相談ください!
歯磨き粉、何で選んでいますか?|スマーク伊勢崎の歯医者さん
2023年12月12日
こんにちは、歯科医師の小林です。
みなさんは、どんな歯磨き粉を使っていますか?
購入する際、何を基準に選んでいますか?
歯磨き粉には様々な成分が入っており、お口に合わせて選ぶことが大切です。
目的に合わせた成分をみてみましょう。
▪️虫歯予防
フッ化ナトリウム、モノフルオロリン酸ナトリウム等
▪️歯周病予防
IPMP(イソプロフィルメチルフェノール)、塩化ベンゼトニウム、トラネキサム酸等
▪️知覚過敏
硝酸カリウム、乳酸アルミニウム等
このほかにも、歯磨き粉には「ペースト」タイプと「ジェル」タイプがあります。
▪️ペーストタイプ
発泡剤が入っており、お口の隅々まで歯磨き粉の成分が行き渡ります。また、研磨剤が入っており、歯の表面の汚れや着色を落とす効果が高いです。泡立ちが良いためすぐにうがいしたくなったり、磨いたつもりになってしまうことがデメリットです。
▪️ジェルタイプ
発泡剤や研磨剤がほとんど入っていないため、薬用成分がお口にとどまりやすく、歯や歯茎を傷つけにくいです。歯の表面の着色が落ちにくく、泡立ちがないため磨いたと実感しにくい方もいます。
現在、歯磨き粉の種類は成分や味等の違いからかなり多くの数があります。
どれを選べば良いか、迷ってしまいますよね。
当院では、「位相差顕微鏡」という特殊な顕微鏡を用いて、お口の中の細菌の種類を確認しています。
細菌の種類や数、活動性によって、おすすめの歯磨き粉の成分が変わってきます。
そのため、この検査をもとに、一人ひとりに合わせた歯磨き粉を提案させていただいております。
歯磨き粉だけでなく、歯磨き指導も行っていますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください。
虫歯って、再発するの?|伊勢崎市の歯科医院
2023年7月20日
こんにちは、歯科医師の小林です。
「虫歯の治療が終わったから、もう安心!」
「また痛くなったら歯医者に行こう」
皆さん、そう思っていませんか?
実は、詰め物や被せ物をしたからといって、安心はできません。
今回は、虫歯の再発についてお話しさせていただきます。
では、なぜ虫歯は再発するのでしょうか?
主な原因をみてみましょう。
①詰め物や被せ物の劣化
詰め物の種類にもよりますが、特に保険適応の素材ですと、年数が経つにつれ劣化しやすいです。金属は熱で膨張・収縮するため隙間ができやすく、錆びたり、金属と歯をくっつけている接着剤が溶け出すこともあります。
徐々に詰め物と歯の間に隙間ができることにより、虫歯菌が入り込み、虫歯が再発してしまいます。
詰め物に隠れた虫歯は確認がしにくく、発見が遅れたり、レントゲンで初めて確認されることもあります。
②歯磨き残しがある
どんなに綺麗に詰め物や被せ物を入れたとしても、残っている歯の部分は虫歯になります。同じ歯でも、異なる場所、特に歯と歯の間から虫歯が再発する方も多くいらっしゃいます。
虫歯を再発させないためには、
・虫歯になりにくい詰め物や被せ物を選択する
・歯科医院での定期的な歯周病治療、ご自宅でのフロスや歯間ブラシの使用
が重要です。
もちろん、一度も削らずに済むことが、再発リスクの低下にもつながります。
“治療したから大丈夫”と思わずに、定期的に歯科医院で確認してもらいましょう。
治療してから10年以上経ったな、心配だな、と思う方は、ぜひ一度ご相談ください。
歯に物が挟まるって、どんなサイン?|伊勢崎市の歯医者
2023年2月6日
こんにちは、歯科医師の小林です。
お食事の際、歯と歯の間に食べ物が挟まるとどうしても気になってしまいますよね。
「以前より歯と歯の間に食べ物が挟まりやすくなった」
「繊維質の物が詰まってしまい、煩わしい」
「もしかして、虫歯?」
そんな悩みを抱えている患者さんも少なくありません。
今回は、なぜ歯に物が挟まるのか、その原因についてお話ししていきます。
①歯と歯の間に虫歯がある
歯と歯の間は歯ブラシだけだとどうしても磨き残しが起きてしまい、気がつかないうちに虫歯になってしまいます。
歯の表面が溶けてザラザラしたり、穴が空いてくると、食べ物が挟まりやすくなります。
②歯茎の位置が下がった
歯周病により歯茎の位置が下がると、歯と歯茎の隙間が広がってきます。
また、歯茎の位置が下がる原因は歯周病だけではありません。
実は、サイズの合わない歯間ブラシを使用したり、誤ったフロスの通し方でも歯茎の位置が下がる原因となります。
③噛み合わせや歯並びに原因がある
歯と歯の間に隙間があいていたり、重なっている部分があると、食べ物が押し込まれやすく挟まる原因になります。
また、噛み合わせや歯ぎしりにより少しずつ歯が動いたりすり減ったりすることでも、食べ物が挟まりやすくなります。
このように、「歯と歯の間に挟まる」といっても原因は1つではありません。
お口に合わせた原因を判断して、治療を行うことが大切です。
また、正しい歯磨きの仕方を学ぶことも非常に重要です。
そのままにしておくと虫歯や歯周病が進行する原因にもなりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。
妊娠中にお口の中に起こるトラブル
2022年12月24日
こんにちは、歯科医師の澤野です。
体調管理が難しい季節ですね。皆様どうぞご自愛くださいませ。
今回は妊娠中にお口の中に起こるトラブルについて一緒に考えていきましょう!
① 歯ぐきの腫れや出血
妊娠中は女性ホルモンの分泌が増えます。
それにより、お口の中の細菌が増える事があり、歯肉炎になりやすくなります。
その状態を放っておくと悪化してしまい、歯周病になる可能性があります。
歯周病になり歯周病菌が血液に入り込むと早産や低体重児出産のリスクが高まるので、注意が必要です。
② 口臭が強くなる
唾液の量が減少したり、女性ホルモンの分泌が変化したりする事で口臭が強くなる傾向にあります。
また、食生活が乱れたり、つわりによって十分な口腔ケアができない事も口臭の原因となります。
③ 虫歯ができやすくなる
つわりや食習慣の変化、唾液量の減少により、虫歯ができやすくなってしまいます。
妊娠中に気を付けて頂きたい事としては、歯周病や虫歯にならないように、口腔内の環境を整える事です。
つわりで口腔内のケアが辛い時は、小さなヘッドの歯ブラシで磨く、香料や味の強い歯磨き粉を避けるなどの工夫をしてみましょう。
また、どうしても磨くのが辛いときはぶくぶくうがいをしてできるだけお口の中の汚れを落とすようにしてみましょう。
ちなみに安定期(4~7か月)は歯科治療や検診に適している時期です。
後期に入ってお腹が大きくなったり、お子さんが生まれて忙しくなった後だとなかなか治療や検診を受けるのが難しくなると思いますので、何かお口の中に不安がある際は、この時期に相談しに来ていただくのがお勧めです。
妊娠中もお子さんが生まれてからも、お母さんのお口の中の環境はお子さんに大きく影響を及ぼします。
我々も全力でサポートいたしますので、普段よりお口の中の環境を整えていきましょう!
歯科治療の麻酔薬|伊勢崎市の歯科医院
2022年11月9日
こんにちは、歯科医師の酒井です。
今回は歯科治療に使われる麻酔薬に関してのお話をしたいと思います。
歯科治療は痛みを伴う処置を伴う処置が多く、患者様のストレスを軽減するために麻酔が必要になる機会が多いです。
麻酔は痛みを和らげるために必要なものではありますが、麻酔処置後に動悸がしたり、気分が悪くなるなど不快症状を認めることがあります。
最近、僕の患者様でも麻酔後にこのような体の異常が見られ、処置を中断した方がいらっしゃいました。
当院では初診時での問診にて、これまでの歯科治療で気分が悪くなったことがないか、麻酔をした後に不快な症状が出たことはないかなどはしっかりと確認してから治療を行います。
しかし今まで特に問題がなくても、久しぶりの麻酔であったり、当日寝不足であったり体調が万全でなかったりすると、予期しない症状が出ることはあるようです。
このような症状は、麻酔の痛みや麻酔に際しての不安などのストレスによるものであったり、麻酔薬に含まれるアドレナリンが原因となっていることがほとんどです。
どちらの場合でも基本的には時間をおくと回復する場合が多いです。
我慢していると状況が悪化する場合もありますので、もし体に不調を感じた場合にはすぐにお声がけください。
回復した後も治療をそのまま続けるか、大事をとって処置を見送るかは自由に決めていただいて大丈夫です。
僕自身も声をかけていただきやすい雰囲気づくりを心がけていきます。
歯茎が下がった|伊勢崎市の歯医者で相談
2022年2月9日
こんにちは、歯科医師の今野です。
女性の患者さんによく相談される悩みのひとつに「歯茎が下がった」ことがあげられます。
つい先日も姉に相談されました。わたしの姉が悩んでいるのは、歯茎が下がったことにより「ブラックトライアングル」が目立ち、むし歯か、歯に汚れがついているかのように見えるのがすごく嫌だ、とのことでした。
さて、歯茎が下がる、とはどういうことで、何が原因なのでしょうか。
歯茎が下がることを「歯肉退縮」といいますが、具体的には次のような悩みにつながります。
① 歯が長く見える
② 歯根が露出する:
もともと歯茎に覆われていた歯根が露出することによって知覚過敏の原因にもなります。
③ 歯がぐらぐらする:
歯肉退縮が悪化すると歯周病が進み、歯が揺れてきてしまうこともあります。
④ ブラックトライアングル:
歯茎が下がったことにより、歯と歯の間の隙間が三角形に黒く見えることがあります。これをブラックトライアングルといいます。
それは、以下のような原因によって引き起こされます。
① 歯周病:
歯肉退縮の主な原因です。歯と歯茎の境の溝から歯周病菌が侵入し、歯の周りの組織や歯を支えている骨が溶かされてしまいます。大抵の場合は痛みもなくゆっくり進行するので、気づいた時には歯が揺れてしまっていた、ということもあります。
② ブラッシングのしすぎ
間違った方法で歯をブラッシングしたり、強い力でブラッシングしすぎてしまうと、歯茎が下がる原因となってしまいます。
③ ホルモン:
女性ホルモンのエストロゲンの濃度が変化することによって、歯茎が敏感になり、歯茎が下がりやすくなることもあります。
④ タバコ:
歯肉退縮の原因となる歯周病が進行するリスクとなります。
⑤ 歯ぎしりや食いしばり:
歯ぎしりや食いしばりによっても歯に過剰な力が加わって歯肉退縮の原因となります。
⑥ 歯並びやかみ合わせの不良
歯が均等にかみ合っていないと、歯や歯の周囲の組織に過剰な力がかかり、歯肉退縮を引き起こします。
⑦ 加齢:
年齢に伴って、病的な退縮とは別に生理的な歯肉退縮が起きることがあります。
一度下がってしまった歯茎は自然に戻ってくれることはありません。外科手術が必要になる場合もあります。
そうなる前に一番大切なのは、健康な歯茎を守れるように定期的にメンテナンスを行うことです。
何かご心配なことがあればお気軽にご相談ください。
歯科と栄養⑥
2022年1月18日
こんにちは。歯科医師の西澤です。
前回、キシリトール(代用甘味料)の良い点についてお話しました。今回、代用甘味料は万能なのかお話していきます。
代用甘味料は血糖値の変化を起こさないことや、むし歯の主な原因菌であるミュータンス菌の餌にならないことをお話しました。
むし歯になるかどうか何で変わるでしょうか?
実はむし歯菌は生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中にはいません。
むし歯菌をご家族や友人などからもらい、感染してしまう感染症の一つなのです。
また、感染しやすい時期というのもあり、これを歯科業界では「感染の窓」といいます。
1歳7か月から2歳7か月までの間にミュータンス菌に感染しやすいことを表したもので、歯の本数が増えミュータンス菌の住家も増えること、他の菌が少なく住みやすいこと、糖を摂取する機会が増えることが主な原因としてあげられます。
この時期に注意することが大切です。
具体的には、乳幼児本人にではなく、親御さんたちができることがあるとするなら、唾液がうつらないようにスプーンの共有をやめたり、冷まし方をフーフーしないように気を付けたり、もしくはキシリトールを用いてむし歯菌を活発にさせないことも有効だと思います。
成長期には部活などでスポーツが盛んになり、スポーツドリンク(500mlにスティックシュガー4本分)を摂取する機会が増えるなど、糖の摂取も増える時期なので、唾液の減る睡眠前に飲まないなどの摂取のタイミングに気を付けたり、水で薄めて糖の濃度を下げるなどしてむし歯菌を活動にも気を付けましょう!
次回は食事の意義についてお話します